『マンション管理員オロオロ日記――当年72歳、夫婦で住み込み、24時間苦情承ります』レビュー|笑って学べる“集合住宅の人間学”
本記事にはプロモーションが含まれる場合があります。購入の参考になれば幸いです。
結論(先に要点/ロングサマリー)
この本は、集合住宅という“小さな社会”を舞台に、72歳の著者が夫婦で住み込み管理員として過ごす日々をユーモラスに綴った現場エッセイだ。ページを開くと、最初に飛び込んでくるのは大事件ではなく、ゴミ置き場のルール、夜間の足音、駐輪区画のはみ出し、エレベーター内のペットの抱き方――生活者なら誰もが一度は体験する“あるある”の数々。けれど著者はそこに善悪や犯人探しの物語を持ち込まない。まず現場を見て、相手の言い分を聞いて、規約という“盾”を掲げる前に、クッションになるひと言を置く。怒りを鎮めるのは正論ではなく、作業工程の透明化であり、「いつ・誰が・何をするか」を明確にする段取りだという視点が芯にある。
管理員の仕事は派手さと無縁だが、だからこそ暮らしの質を底上げする。張り紙の文面を一行短くする、掲示の位置を導線上に移す、返答の期限を先に示す――小さな工夫が積み重なると、匿名の怒りは行き場を失い、住民の“近さ”が戻ってくる。著者は度々“オロオロ”すると書くが、その揺らぎがむしろ人間的で、読む側の肩の力を抜いてくれる。失敗も笑いに変える管理室の会話、夜勤明けの静けさ、夫婦の掛け合い。読後に残るのは、規約の暗記ではなく、「正しさより近さ」「原因追及より再発防止」「善意より仕組み」という姿勢で、今日から自分の住まいに優しくなれる感覚だ。マンションの理事や管理会社に関わる人だけでなく、接客やクレーム対応に携わる人にも“現場の勘所”を教えてくれる一冊である。
どんな本?
舞台は管理室。24時間、日常と非常が交差する場所で、著者夫婦は住民、理事会、管理会社のあいだを行き来しながら、日々の“ささやかな事件”に向き合う。日記風の語り口は軽く、笑いも多いが、エピソードの奥には「人はこう動く」「だからこう受け止める」という実践知が通底している。専門用語や説教は徹底して少なく、生活者の言葉で可笑しみと示唆が同居する。
こんな人に刺さる(最小限)
-
集合住宅に住み、掲示やルール運用の現実が気になる人
-
マンションの理事・管理組合・管理会社に関わる人
-
接客やクレーム対応の“効くさじ加減”を実感で学びたい人
現場から見える“効く対処”のコツ
まず著者は、通報や噂に頼らず自分の足で現場を見る。音の苦情なら時間帯と音種を分けて記録し、事実を積む。次に、規約を盾にする前に、クッションになる声かけを挟む。「教えてください」「困ってますか?」から始めるだけで、相手は“敵”から“隣人”に変わる。貼り紙は短く、太く、やさしく。説教調をやめ、目的と行動だけを端的に。匿名の怒りには工程で応える。“誰が・いつまでに・何をするか”を先出しし、返答の期限を明記すれば、感情の熱は自然と落ち着く。こうした小さな段取りが、秩序を守る最大の武器になる。
ケースで読む“集合住宅のあるある”
ゴミ置き場
曜日無視や分別のグレー、粗大物の“置き逃げ”は、張り紙の文言を強くするほど反発を招きやすい。著者は掲示の場所を導線上に変え、OK手順をイラストで見せ、一回目は声かけ、二回目から記録という段階設計で効かせる。
騒音
上下左右の“正義”がぶつかる騒音は、感情での押し合いを避け、時間帯×音種でルールを明確化。測定・記録を前提に話し、謝罪の儀式より再発防止策を先に置くと、対話が前に進む。
駐車・駐輪
一台の“ちょいはみ出し”が全体の秩序を崩す。ペイントや矢印で枠と導線を再設計し、一斉張り紙に頼らず個別対話を重ねる。罰則だけでなく“罰の前の段階”を増やすことが抑止に効く。
ペット
可愛さと迷惑の境界で揉めやすい。エレベーター内の動線をルール化し、抱きかかえ表示を見やすく配置。鳴き声の再発時は“鳴き止み行動”チェック表で対話の土台を共有する。
夫婦チームの働き方に学ぶ
フロント(対話)とバックヤード(清掃・記録・備品管理)の役割を分け、毎日の軽作業を“運動”としてスケジュール化する。メンタル面ではユーモアの共有と“今日の良かったニュース”の報告を習慣にし、100点より85点を毎日続ける。高齢であっても、仕組み化と分担で成果は積み上がることを体現している。
“人間関係の公式”はこうだ
著者が繰り返し示すのは、正しさより近さ、原因追及より再発防止、そして善意より仕組み。誰かの善意に期待し続ける運用は、その人が休んだ瞬間に崩れる。仕組みで回せば、個人の負担は軽く、品質は安定し、トラブルは減る。集合住宅は縮図であり、職場や家庭にもそのまま持ち込める視点だ。
明日から使える“小さな工夫”(最小限の箇条書き)
-
張り紙は見出しを行動命令文にし、本文は三行以内
-
相談には“返答の期限”を先に伝え、工程を共有
-
月末に「今月の助かったこと」を三つだけ数えて掲示
読み方ガイド
通勤時間には苦情対応の軽妙なエピソードを一話ずつ。週末には理事会や規約運用の章をまとめ読みして、自宅の掲示や導線設計に落とし込む。最後に夫婦の掛け合いを味わえば、続けるためのユーモアの効き目に気づけるはずだ。
心に残る場面
張り紙ひとつで空気が変わる瞬間、匿名メモの矛先が工程の共有でスッと収まる過程、夜間の見回りで“ただそばにいる”ことが支えになる実感――どれも小さな出来事だが、暮らしの質を確かに上げていく。失敗も笑いに変える管理室の温度が、読者の心までほぐしてくれる。
まとめ
これは“管理”の本であると同時に、人を大切にする生き方の本だ。大声の正論より、小さな工夫と段取りが街を平和にする。読後、掲示板の一枚、あいさつのひと言、返答のひと手間が変わる。そんな静かな変化を、あなたの住まいにも。

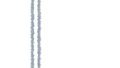
コメント